2026年度労働基準法改正のポイント|人事労務に必要な対応とは
2026年度に向けて、労働時間や休日の取り扱い、有給休暇の賃金算定など、労働基準法制に関わる重要な改正が検討されています。
厚生労働省の研究会報告書に示された提言は、まだ法案段階ではありませんが、今後の国会審議を経て法制化される可能性が高いものです。
これらの改正は単なる法令変更にとどまらず、企業の勤怠管理・就業規則・シフト運用・給与計算など、現場実務に直接大きな影響を与える内容です。
「改正が決まってから準備」では間に合わず、今から社内制度や運用の点検を始めておくことが重要です。
厚生労働省の研究会報告書では、人事労務の現場に大きな影響を及ぼす複数の法改正が提言されています。
ここでは、その中でも企業が押さえておくべき主要な7つの論点について整理します。
連続勤務の上限規制(14日以上連勤禁止)
概要
「14日を超える連続勤務を禁止する」方向性が示されています。労働者の健康確保の観点から、長期連勤を制限する制度改正です。
改正の背景
- 現行制度では「毎週1日または4週4日休めばOK」とされ、28連勤や48連勤も理論上可能。
- 一方、労災認定基準では「14日以上連勤」は強い心理的負荷とされ、制度とのギャップがあった。
見落とされやすい盲点
- 夜勤のカウント方法:
夜勤専従は「1勤務=1日」と扱うが、日勤+夜勤混在者は暦日単位でカウントするため、感覚よりも早く「14日連勤」に達してしまう。 - 休みと認められないケース:呼び出し・研修・自宅待機などは実態が労働と判断されれば勤務日扱い。
- 管理監督者の扱い:休日規制は適用除外だが、労災認定基準上はリスクとして評価される。
企業がとるべき対応
- 勤怠システムに「連勤チェック機能」を導入
- 繁忙期や欠員に備え、応援要員・短期アルバイト・派遣などを確保
- 管理職に業務が集中しないよう分散
- 就業規則に「連続勤務上限」を明文化
法定休日の明確な特定義務
概要
「週1日の法定休日を事前に特定して明示する」ことを義務化すべきとされています。
改正の背景
- 現行制度では「結果的に週1日休めばOK」で、休日を事後的に割り当てる運用が可能だった。
- 労働者から見て「いつ休めるのか」が不透明で、働き方の見通しが立てにくい。
見落とされやすい盲点
- 休日と所定休日の区別:週休2日の場合、どちらを法定休日とするかを必ず明示。
- シフト制の現場:従業員ごとにシフト表に法定休日を明記する必要がある。
- 週の起算日:決めていないと自動的に日曜始まりとみなされる。
企業がとるべき対応
- 就業規則・年間カレンダーに法定休日を明示。
- シフト制では、各従業員ごとにシフト表に法定休日を記載。
- 勤怠システムで法定休日と所定休日を区別。
- 現場責任者への教育を徹底し、誤ったシフト運用を防止。
勤務間インターバル制度の義務化
概要
勤務終了から次の始業までに一定時間(例:11時間)の休息を確保する制度を、努力義務から法的義務に格上げ。
改正の背景
- 現行は努力義務であり、残業や夜勤明けで十分な休息が取れないケースが多い
- 過労死防止や健康確保のため、強制的な仕組みが必要とされている
見落とされやすい盲点
- 会議や研修も労働時間に含まれるため、インターバル不足になりやすい
- 在宅勤務でも対象となる
- 就業規則に「始業・終業を繰り下げできる」条項がなければ調整できない
企業がとるべき対応
- 勤怠システムにインターバル自動チェック機能を導入
- シフト作成や業務計画段階から「11時間以上の休息」を前提に組む
- 就業規則を改訂し、始業・終業の繰下げを可能にする。
- 管理者に教育を行い、研修や会議の設定が違反を招く可能性を理解させる
有給休暇の賃金算定方式(通常賃金方式の原則化)
概要
有給休暇を取得した際の賃金は、通常の賃金方式を原則とする方向が示されている。
改正の背景
- 平均賃金方式や労使協定方式では低額になるケースが多く、「有休を取ると損」という不満の要因になっていた
見落とされやすい盲点
- 労使協定方式は「通常賃金と乖離する低額処理」は認められない可能性が高い
- 歩合給や変動シフト職種も「例外扱い」は難しくなり、通常賃金に含める範囲を整理する必要がある
企業がとるべき対応
- アルバイトやシフト勤務者の有休処理ルールを見直す
- 給与計算システムを点検し、通常賃金方式に対応させる
- 歩合給や変動シフト職種について、通常賃金に含める範囲を明確化
- 労使協定を利用している企業は、内容が通常賃金と乖離していないか点検・改訂
- 小売・飲食業など影響が大きい業種は、人件費増加の試算を行い経営計画に反映
つながらない権利(勤務時間外の連絡制限)
概要
勤務時間外に業務上の連絡に対応しない権利を保障するため、ガイドラインを策定。
改正の背景
- 現行法には規定がなく、勤務時間外のメール・電話に応答する「暗黙のプレッシャー」が強い
- 在宅勤務の普及で、どこから勤務時間外なのか不明確になりやすい
見落とされやすい盲点
- 一律禁止ではなく、緊急時や顧客対応など合理的に必要な連絡は残る
- ガイドラインだけでは不十分で、社内ルールに落とし込まないと形骸化する
- 管理職層の意識不足により、制度が有名無実化する恐れがある
企業がとるべき対応
- 就業規則や社内規程に勤務時間外の連絡原則禁止を明記
- 緊急連絡ルート(当番制・ホットラインなど)を設ける
- 管理職教育を行い、勤務時間外の連絡を強要しない文化を作る
- 在宅勤務規程と連動させ、勤務と私生活の切れ目を明確化する
副業・兼業の労働時間通算ルールの見直し
概要
複数事業場での労働時間を通算して割増賃金を算定するルールを見直す。
改正の背景
- 労基法38条は「1日8時間」「週40時間」を超えた場合、後から雇った会社が割増を払うと規定。
- しかし、副業先が本業の労働時間を把握することは現実的に不可能。
- さらに、本業=変形労働、副業=フレックスのように制度が異なると通算不能。
見落とされやすい盲点
- 割増賃金の負担は軽減されても、労災や過労死認定は労働時間を合算して判断される。
- 就業規則で副業を認めても、労働時間や健康状態の申告ルールがなければリスクは残る。
企業がとるべき対応
- 就業規則に副業条件・申告義務を明記。
- 定期的に労働時間・健康状態を確認する仕組みを整える。
- 管理職・人事担当者に「副業時間も含めた合算で健康管理が必要」と教育。
法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
概要
商業・サービス業など常時10人未満の事業場で認められている「週44時間特例」を廃止し、週40時間に統一。
改正の背景
- 同じ業務でも事業場規模で法定労働時間が異なるのは不公平。
- 働き方改革の流れにも逆行する規定。
見落とされやすい盲点
- 44時間前提でシフトを組んでいた事業場は、人員増強や労働時間削減が必要。
- 週40時間超の労働が時間外扱いになり、残業代コストが増加する。
- 「常時10人未満」を基準にしていた会社は一律で週40時間対応が求められる。
企業がとるべき対応
- 就業規則を改訂し、週40時間に統一。
- 勤務シフトや業務を見直し、人員増強や効率化を検討。
- 人件費増加の試算を行い経営計画に反映。
- 現場責任者に教育し、誤解に基づく運用を防ぐ。
まとめ
研究会報告書で示された改正論点は、いずれも「現行制度の不合理を正す」だけでなく、労働者の健康確保や働き方改革をさらに進めることを目的としています。
一方で、企業にとっては人件費の増加やシフト編成の難化など、具体的な対応を迫られる改正でもあります。
- 勤怠管理システムの見直し
- 就業規則や社内規程の改訂
- 管理職・現場責任者への教育
- 制度変更に伴うコスト試算
こうした準備を先手で進めることで、改正が施行された際にもスムーズに対応できます。
無料相談のご案内
HR designでは、法改正対応や就業規則の整備、勤怠管理の運用改善について、無料相談を承っています。
「うちの会社はどこから手をつければいいのか知りたい」といった段階でもお気軽にご利用ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 NEWS2026-01-20管理職と管理監督者は同じではない
NEWS2026-01-20管理職と管理監督者は同じではない NEWS2026-01-132025–2026年「年収の壁」をどう整理するか
NEWS2026-01-132025–2026年「年収の壁」をどう整理するか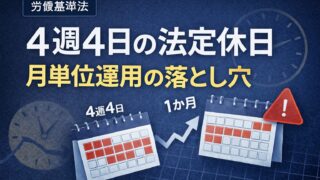 NEWS2026-01-06「4週4日の法定休日」
NEWS2026-01-06「4週4日の法定休日」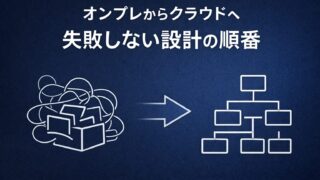 NEWS2025-12-23人事管理システムをオンプレからクラウドへ
NEWS2025-12-23人事管理システムをオンプレからクラウドへ


