【人事労務のプロが解説】同意書が必要な場面と実務対応(2025年版)
✅ まず押さえる!同意が必要かどうかの3ステップ
- 労働条件を変える?
→ 特に「不利益変更」や「新しい義務・費用負担」があるなら、個別同意が必要。 - 就業規則で対応できる?
→ 合理性があれば同意不要だが、重要条件は同意を取ると安全。 - 同意では足りないケース?
→ 賃金控除やフレックスなどは、労使協定や届出が必須。
✅ A. 個別同意が「必ず必要」なケース
- 給与や手当を下げる場合
例:基本給の減額、固定残業代の時間数を減らす
→ 労契法8・9条(不利益変更は合意が原則) - 勤務地や職種を契約で限定している場合の異動
例:「勤務地:東京のみ」と契約書に明記
→ 判例法理(限定合意があると同意必須) - テレワークで新しい負担や義務を課す場合
例:通信費を自己負担、監査ツール導入
→ 厚労省ガイドライン(条件変更は合意が望ましい) - 個人情報の取り扱いで法令上同意が必要な場合
例:健康情報の取得、海外クラウドへのデータ移転
→ 個人情報保護法(本人同意が原則)
✅ B. 同意は不要だが「取ると安全」なケース
- 就業規則の不利益変更(合理性あり)
例:退職金規程の見直し、賞与評価の変更
→ 労契法10条(合理性があっても説明+同意が安心) - 転勤(限定合意なし)
例:包括的配転条項あり、業務上必要
→ 判例法理(濫用でなければOKだが、生活影響大なら同意推奨) - 副業・兼業の制限や届出
例:競業禁止、事前届出制
→ 厚労省ガイドライン(必要最小限+透明性)
✅ C. 同意書では足りない=「協定や届出」が必要なケース
- 賃金からの法定外控除
例:社宅費、食費
→ 労基法24条(24協定が必須、同意だけではNG) - フレックスタイム制の導入
→ 労使協定+就業規則の整備が必要 - 事業場外みなし労働時間制
→ 労基法38条の2(要件確認+協定)
✅ テレワークの誤解しやすいポイント
- 導入自体は同意不要
ただし、場所・時間・費用・セキュリティを変えるなら同意を取ると安全。 - 中抜けやフレックス
→ 就業規則や労使協定でルール化が必要。
✅ 実務チェックリスト(6項目)
- 変更内容を棚卸し(給与・勤務地・時間・費用・情報管理)
- A/B/Cどの類型か判定
- 必要な手続(同意書・協定・規程改定)を確認
- 説明資料を準備(自由意思・質問機会を確保)
- 書面で同意・協定を取得し保管
- 運用後のモニタリングと見直し
✅ まとめ
- 不利益変更や新しい義務=個別同意が原則
- 就業規則変更で対応できても、重要条件は同意を取ると安全
- 同意では足りない領域(賃金控除・フレックス等)は協定必須
- テレワーク・副業はガイドラインに沿って透明性を確保
✅ HR designができること
電子契約・クラウド管理の導入支援
労務DXツール(SmartHR等)を活用した契約・同意管理の仕組みづくり。
契約書・同意書の作成サポート
不利益変更、テレワーク、副業、個人情報など、実務に即した文面を作成。
就業規則・規程の改定支援
テレワーク規程、副業規程、賃金規程など、最新法令・ガイドライン対応。
労使協定の整備
賃金控除協定(24協定)、フレックス、みなし労働など、必要な協定を作成。
説明資料・社内研修の提供
従業員説明会用スライド、管理職向け研修、Q&A集の作成。
「このケース、同意書が必要?」と迷ったら、早めの相談がトラブル防止のカギです。
HR designは、契約書・同意書の整備から、就業規則改定、労使協定、説明会サポートまでワンストップで対応します。
まずはお気軽にご相談ください。
▶ お問い合わせはこちら
出典
- 労働契約法8〜10条(契約変更・合理性)
- 労基法24条(賃金控除)、38条の2(みなし労働)
- 厚労省「テレワークガイドライン」
- 厚労省「副業・兼業ガイドライン」
- 個人情報保護法ガイドライン
- 配転命令権の判例法理(限定合意の有無)
無料相談について
ご不明点や個別のご相談がありましたら、
無料相談をご利用ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 NEWS2026-01-20管理職と管理監督者は同じではない
NEWS2026-01-20管理職と管理監督者は同じではない NEWS2026-01-132025–2026年「年収の壁」をどう整理するか
NEWS2026-01-132025–2026年「年収の壁」をどう整理するか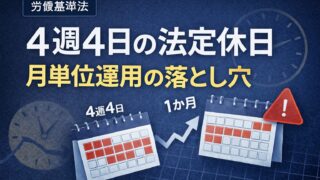 NEWS2026-01-06「4週4日の法定休日」
NEWS2026-01-06「4週4日の法定休日」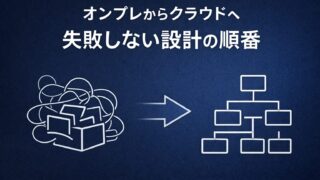 NEWS2025-12-23人事管理システムをオンプレからクラウドへ
NEWS2025-12-23人事管理システムをオンプレからクラウドへ

