「未払い残業リスク診断|5つの落とし穴とセルフチェック」
「残業代を払っていないわけではないのに、なぜ“未払い残業”と指摘されるのか?」
企業にとって未払い残業は、思わぬタイミングで大きなリスクとなります。
労働基準監督署からの是正勧告で数百万円〜数千万円の遡及支払いを命じられるケースや、裁判で労働者の主張が認められるケースも少なくありません。
さらに、経営者個人に対しても刑事責任が問われる可能性があります。
本記事では、未払い残業につながる「よくある5つの落とし穴」 を取り上げ、リスクの具体例と対策を解説します。
記事の最後に、御社の状況をセルフチェックできるPDF診断もご用意していますので、ぜひ合わせてご活用ください。
落とし穴① 36協定を結んでいない
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・週40時間以内と定められています。
これを超えて従業員に時間外労働をさせるためには、**労使協定(36協定)**を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
36協定を結ばずに残業を命じてしまうと、
- 会社としては「残業をさせた」という事実だけが残る
- 協定がないため、その残業は「違法な時間外労働」とされる
- 労基署の調査が入ると、是正勧告や罰則の対象になる
といった事態に直結します。
実際、労基署の調査で「36協定が未締結」の状態が発覚し、遡って未払い残業代を全額支払うよう命じられた企業も存在します。
「少人数だから」「形式的なものだから」と軽視するのは極めて危険です。
落とし穴② 残業時間を正確に集計できていない
「勤怠打刻はしているから大丈夫」と思っていても、集計方法が不十分だと未払い残業の温床になります。
労働基準法では、時間外労働について 月45時間・年360時間 の上限が設けられています。
さらに、特別条項付き36協定を結んでいても、
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内
- 月100時間未満
といった厳格な制限があります。
これを超えてしまうと「過労死ライン」とされ、労基署からの是正勧告や労災認定リスクに直結します。
しかし、実務では次のようなケースで誤集計が発生しがちです。
- システムが休憩時間を自動控除してしまい、実際の労働時間より短く算出されている
- 管理者が「サービス残業」を慣例的に黙認している
- シフト勤務で「早出」「居残り」が集計から漏れている
これらはすべて「会社が労働時間を正しく把握していなかった」と判断され、遡及して残業代を支払う義務が発生します。
落とし穴③ 固定残業代の運用ミス
「うちは固定残業代を払っているから大丈夫」と安心していませんか?
実は、固定残業代の設定や運用を誤ると、未払い残業が発生したとみなされるリスクがあります。
典型的な問題点は次の通りです。
- 就業規則や雇用契約書に「固定残業代が何時間分なのか」を明記していない
- 金額の算定根拠が不透明で、何を基準にしているか説明できない
- 実際の残業時間が固定残業時間を超えても、追加の残業代を払っていない
裁判例でも「固定残業代の内訳が不明確」であったために無効と判断され、固定残業代を払っていたのに、さらに残業代を二重払いする羽目になった企業があります。
つまり、固定残業代は適切にルール化し、残業時間が超過した場合には必ず追加で支払うことが不可欠です。
「制度を導入しているから安心」ではなく、運用が正しくできているかを点検することが重要です。
落とし穴④ 割増率の計算ミス
残業代は「時間単価 × 割増率」で計算されます。
しかし、この割増率を誤ると、本来払うべき金額より低くなり、未払い残業扱いとなります。
労基法で定められた割増率は以下の通りです。
- 時間外労働(1日8時間・週40時間を超える分):25%以上
- 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上
- 休日労働(法定休日に勤務):35%以上
たとえば、法定休日の深夜労働であれば「35%+25%=60%」の割増が必要です。
ところが実務では、休日割増と深夜割増を正しく合算せず、35%しか支払っていなかったといったケースが頻発しています。
また、時給換算の基礎賃金の算定を誤っていると、割増率が正しくても金額が不足することになります。
このような計算ミスは、1人あたり数千円の差でも、従業員数 × 年数分として積み重なり、最終的には数百万円単位の請求につながることがあります。
落とし穴⑤ 労働時間の記録を残していない
「勤怠管理は自己申告だから」「残業は管理職が見ているから大丈夫」と考えていませんか?
労働時間の記録を適切に残していない場合、裁判や労基署の調査で会社側が圧倒的に不利になります。
実際の裁判では、
- 従業員がつけていた 手帳やメモ
- スマホのスクリーンショットやチャット履歴
といった証拠が「労働時間を示す記録」として採用された例があります。
一方で、会社側にタイムカードやシステム上の記録が残っていなければ、労働者の主張がそのまま認められやすいのです。
結果として、会社が想定していなかった長時間労働を前提に、残業代や慰謝料の支払いを命じられることもあります。
未払い残業のリスクを防ぐためには、
- 打刻システムやICカードによる客観的な記録
- 残業申請と実績の突き合わせ
- 管理職による確認・承認フロー
といった仕組みを整えることが欠かせません。
判定の目安
ここまで紹介した5つの落とし穴、御社はいくつ当てはまりましたか?
「いいえ」が1つでもある場合、その時点で法令違反や是正勧告につながる可能性があります。
- 「いいえ」が0個 → 適法に運用できている可能性が高い
- 「いいえ」が1〜2個 → すでに法令違反の恐れあり(要是正)
- 「いいえ」が3個以上 → 高リスク(是正勧告・遡及請求の危険が極めて高い)
まとめ
未払い残業の怖さは「気づかないうちに発生している」ことです。
36協定の不備、勤怠集計のミス、固定残業代の誤運用など――
いずれも現場では「よくあること」として放置されがちですが、ひとつでも抜け漏れがあれば法令違反として指摘される可能性があります。
「御社はいくつ当てはまりましたか?」
気づいた段階で放置せず、改善のための第一歩を踏み出すことが重要です。
📝 セルフ診断はこちらから(PDFダウンロード)
👉 https://hrdesign.or.jp/download/
💬 専門家による無料相談(60分)も承っています
記事を読んで不安を感じた方は、ぜひご利用ください。
御社の状況をヒアリングし、具体的な改善の方向性をご提案します。
👉 https://hrdesign.or.jp/consult/
投稿者プロフィール
最新の投稿
 NEWS2026-01-20管理職と管理監督者は同じではない
NEWS2026-01-20管理職と管理監督者は同じではない NEWS2026-01-132025–2026年「年収の壁」をどう整理するか
NEWS2026-01-132025–2026年「年収の壁」をどう整理するか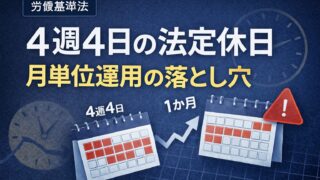 NEWS2026-01-06「4週4日の法定休日」
NEWS2026-01-06「4週4日の法定休日」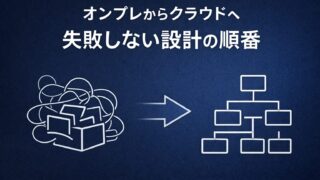 NEWS2025-12-23人事管理システムをオンプレからクラウドへ
NEWS2025-12-23人事管理システムをオンプレからクラウドへ

